その13~マジック:ザ・ギャザリングでボードゲームを遊んでみよう【灰色熊の冒険】
●なんでもできるぞマジック:ザ・ギャザリング
マジック:ザ・ギャザリングには無限の可能性がある。
俺より若干強い奴に会いに行く。
最高峰の競技的対戦要素。
コレクションを眺めてニヤニヤしたい。
膨大な種類を誇る収集要素。
友達100人作ってやるぜ。
ゲームを通じてのコミュニケーション要素。
創作界の神におれはなる。
二次創作によるコンテンツ要素。
なんならマジックを通じて恋人を見つけたり、職を手にした人もいる。
そう、マジック:ザ・ギャザリングはなんでもできるのだ。
なんでもできる。
マジック:ザ・ギャザリングのカードだけでボードゲームもできる。
はい!!
マジック:ザ・ギャザリングのカードを使ったボードゲームと言えばこれですね!!

ロゴデザイン:わたくし
というわけで今回はボードゲーム「灰色熊の冒険」を現代風にリメイクしたゲームを考案したので紹介します!
リメイクしても名前は「灰色熊の冒険」です。
現代社会の辛い現実に揉まれて、人としてどんなに薄汚れても原作へのリスペクトだけは忘れてはいけないので。
●灰色熊の冒険って何よ
卑猥の化身氏の動画シリーズ「灰色熊の冒険」に登場する「ボードゲーム『灰色熊の冒険』」を指します。
ややこしいので以降は「元祖灰色熊の冒険」と呼称します。
今回紹介する「灰色熊の冒険」はこのゲームをベースに作成しています。
ざっくり説明すると、マジックのカードを使ってモノポリーのようなことをして勝利点を集めるゲームです。
卑猥の化身氏の動画が俺たちの青春だったアラサー世代のプレイヤーも、最近始めたルーキーも、先に灰色熊の冒険シリーズを全部見返すことをおすすめします。
●ルール説明・・・の前に
今回は『フォーゴトン・レルム探訪』のカードプールのみを使用しています。
TRPG感あふれるフォーゴトン・レルムを灰色熊が冒険します。
●ルール説明
ルールはこちらでPDFにもまとめてあります。
灰色熊の冒険ルールブックver1.0.pdf
●ゲームの概要
《灰色熊/Grizzly Bears》になって、マップを周回し、強力なクリーチャーと戦ったり呪文を唱えたりして宝物を5つ集めるのが目的です。
5つ集めた瞬間に勝利となります。
3人からプレイできますが、4人でのプレイを推奨します。
※赤字はフォーゴトン・レルム探訪バージョン専用の追加ルール
●準備
《灰色熊/Grizzly Bears》、もしくはそれに準ずるカードを用意します。
《灰色熊/Grizzly Bears》を除いた60枚のデッキを用意します。
初期手札としてカードを3枚引きます。
プレイヤー1人につき、3枚の手札で3マスの道を作ります(4名でプレイした場合12マス)
プレイヤーの正面にあるマスの隅がそのプレイヤーのスタート地点(ホーム)になります。
ゲーム開始時の状態は以下のようになります。
.jpg)
●ゲームの進行~ターンの進行~
ゲームは以下の流れで進行します。
ターン開始→第1メインフェイズ→ダイスを振る→カードをめくる→戦闘orカードのキャスト→マスの補充→第2メインフェイズ→ターン終了→クリンナップステップ
手札から唱える呪文は1ターンに1回唱えることができます。
○ターン開始
ターン開始時に手札が0枚ならカードを1枚引きます。
ゲームに特に影響はありませんが、「アンタップ・ステップ→アップキープステップ→ドローステップ」が存在します。
○第1、第2メインフェイズ
エンチャント、アーティファクトを唱える。装備品を装備する。ソーサリーを唱えるといった通常のマジックと同じ行動が行えます。
○ダイスを振る
6面ダイスを振り、出た目のマス分時計回りに進みます。
ダイスを振ってからカードがめくれるまでは呪文を唱えることはできません。
ダイスを振る代わりに、「ダッシュ」という特殊な行動を行えます。
→[特殊な行動-ダッシュ-]
○カードをめくる
マスにあるカードをめくり、出たカードによってイベントが発生します。
カードをめくる前に同じマスに他のプレイヤーがいる場合、アクティブプレイヤーは1人選んで共闘を提案できます。
→[ゲームの進行~共闘~]
→提案されたプレイヤーは、受けるかカードを1枚渡して拒否することができます(手札が無い場合は拒否できません)
めくれたカードがクリーチャーなら戦闘を行います。
→[ゲームの進行~戦闘~]
めくれたカードがクリーチャー以外ならその呪文を唱えるか墓地に送るかを選びます。
その後ライブラリーから1枚マスにカードを設置します。共闘したプレイヤーはカードを1枚引きます。
○ターン終了
ターンを終了します。
次の手番のプレイヤーが唱えた「ターン終了時まで」という効果はここで終わります(後述)。
○クリンナップステップ
手札が4枚以上の場合、3枚になるまでカードを捨てます。
●ゲームの進行~戦闘~
めくれたカードがクリーチャーなら戦闘を行います。
めくれたクリーチャーがCIP能力を持っていたのならめくれた時に誘発します。この時カードに書かれている「あなた(オーナー)」は戦闘中かどうかを問わずターンプレイヤーです。
→めくれたクリーチャーが攻撃誘発・ブロック誘発能力を持っていたら、ダメージ解決前に誘発します。
・戦闘で勝利した場合
→カードを1枚引き、+1カウンターを獲得します。その後手札から1枚マスにカードを設置します。
・戦闘で敗北した場合
→乗っているカウンターを失い、オーラは墓地へ行き、装備品ははずれ、コマはホームに戻ります。
・戦闘で相打ちした場合
→[戦闘で敗北した場合]の処理の後に[戦闘で勝利した場合]の処理を行います。
・戦闘以外でめくれたクリーチャーを死亡させた場合(めくれたクリーチャーの誘発型能力による破壊も含む)
→カードを1枚引き、手札から1枚マスにカードを設置します。+1カウンターは獲得できません。
・死亡以外でめくれたクリーチャーが戦場を離れた場合
→ライブラリーの1番上からマスにカードを設置します。
●ゲームの進行~共闘~
同じマスに自分以外の2人以上のプレイヤーがいても、共闘できるのは1人のプレイヤーだけです。
共闘していた場合、共闘に選ばれたプレイヤーはアクティブプレイヤーと同様の勝利ボーナスと敗北ペナルティを行います。ただしマスにカードは設置しません。
共闘した場合、2体のクリーチャーは1体のクリーチャーとして扱います。
→例1:めくれたクリーチャーのパワーが3で、自分と共闘者のタフネスがそれぞれ2なら自分も共闘者も生き残ります。
→例2:めくれたクリーチャーのパワーが1で接死を持っていた場合、自分と共闘者ともに死亡します。共闘中にめくれたクリーチャーを呪文等で破壊させた場合、ボーナスを得るのは呪文を唱えたプレイヤーのみです。
討伐ボーナス(後述)や、めくれたクリーチャーが墓地に置かれた際の効果等はターンプレイヤーのみが影響を受けます。
●ゲームの進行~周回ボーナス~
周回してコマがホームを通過する場合、ホームを踏んだ瞬間に以下の行動を行います。
・カードを1枚引く
・宝物を1つ獲得する
・+1カウンターを獲得する or ダンジョン探索を行う
●特殊な行動-ダッシュ-
ダイスを振る代わりに、手札のカードを1枚捨てることでダッシュを行い、捨てたカードのマナコスト分コマをすすめることができます。
ただしそのターン以下のボーナスを得ることができません。
・周回ボーナスは発生しません
・めくったクリーチャーを倒した際にカードを1枚引くことができません
→共闘をして共闘に選ばれたプレイヤーは通常通りのボーナスを得られます。
●通常のMTGと違う挙動、特別ルール
・討伐ボーナス:ドラゴンを死亡させた場合、宝物を1つ獲得します
・「ターン終了時まで」は次の自分のターンの直前まで継続します
・「対戦相手(プレイヤー)」を表す効果を『盤面』に任意に反映させることができます
→布告系除去の生贄や「対戦相手がコントロールクリーチャー」としてマス上に公開されているクリーチャーを対象に選ぶことができます
・追放されたカードはターン終了時に墓地に移動します
・「クリーチャーX体を対象とする。それをタップする。そのクリーチャーは、次のそれのコントローラーのアンタップ・ステップにアンタップしない。」は「そのプレイヤーの次のターンを飛ばす」に置換します
・「あなたがコントロールするクリーチャー」は自分の《灰色熊/Grizzly Bears》と、プレイヤーのコマが置いてあるマスにいるクリーチャーを指します
●その他ルール
・ライブラリーが無くなったor残り枚数が占術等で影響する範囲を下回った場合、墓地をシャッフルしてライブラリーにします
・灰色熊、アーティファクト、エンチャント、宝物・トークン等はコントロール下にあるパーマネントです
→宝物・トークン等はアーティファクト破壊で破壊でき、パーマネントとして生贄に捧げることもできます
・戦闘中は戦闘に参加しているクリーチャー全て「攻撃しているクリーチャー」「ブロックしているクリーチャー」です
・ライブラリーと墓地は共有です
・何らかの理由で手札からマスにカードを置けない場合、ライブラリーの1番上のカードを代わりに置きます
・マスのカードは裏向きである間はあなたがコントロールする土地として扱います
●無視する概念
・ライフは存在しません(無限にあると思ってください)
・マナコストの支払いは考慮しません(無限にあると思ってください)
→唱える際の追加コスト等でマナやライフの支払い以外が存在する場合、それは支払います。
・トークン生成は行われません
・めくられたクリーチャーの起動型能力は起動できません
ターンが経過すると以下のような感じになります。
.jpg)
●デッキサンプル
あくまでサンプルです。
自分が面白いと感じたカードを好きにぶちこんでもええんやで!
●灰色熊の冒険 フォーゴトン・レルム探訪Verのカード解説
●実際に遊んでみよう
百聞は一見にしかず! というわけで実際に遊んでみよう!!
今回はルールや採用カードの調整を実施したテストプレイの様子をご紹介します。
メンバー紹介
 |
|
めぐすけ(オレンジのコマ)
「大会後に灰色熊の冒険やるから付き合って」という謎のメッセージをSNSに発信した。
新年一発目にマイナーフォーマットであるパウパーの記事を書く暴挙に飽き足らず
秋葉原駅前店開店直後のコラム一発目が”これ”なのでドラゴンスターに命を狙われている。
(編注:狙ってません) |
 |
|
T(緑のコマ)
学生時代にめぐすけと共に卑猥の化身氏の動画を見漁っているため灰色熊の冒険のルールは把握している。
デッキはこちらで用意すると言ったにも関わらず自前で100枚デッキを持ち込みメンバーにプレイさせ
装備品を多く採用するといかにゲームバランスが崩れるかをメンバーに伝えた。 |
 |
|
N(紫のコマ)
灰色熊の冒険は全く知らないが、大会の合間に当日渡したルールブックを全部ちゃんと読んでルールを覚えるという
「現代人の活字離れ」に真っ向から立ち向かう凄まじいプレイを見せつけ、めぐすけを驚かせた。 |
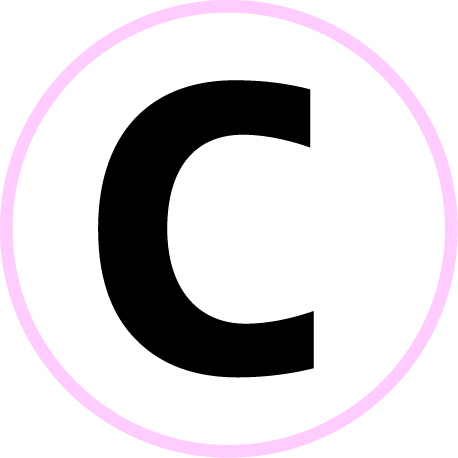 |
|
C(ピンクのコマ)
当日大会に寝坊して不参加かと思われたが、「灰色熊の冒険やるから来て」とめぐすけが連絡したら
灰色熊の冒険をやるためだけにわざわざ会場まで来た超絶やる気勢。 |

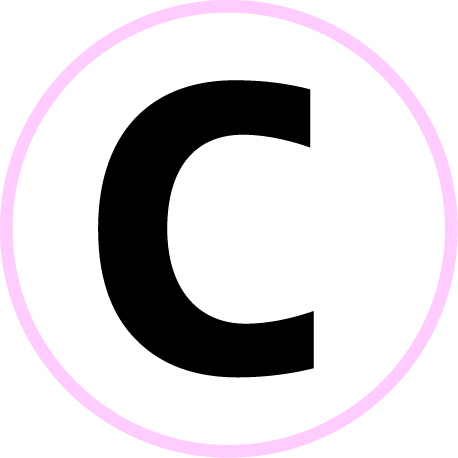 |
|
お、同じマスに止まった。この場合共闘を選べるのか。じゃあ現在3/3のめぐすけさん共闘しますか。 |
 |
|
OKです。めくれたのは《アウルベア/Owlbear》です!◇
1人では一方的にやられてしまいますが、2人で力を合わせれば勝てるのです! 努力! 友情! 勝利! |
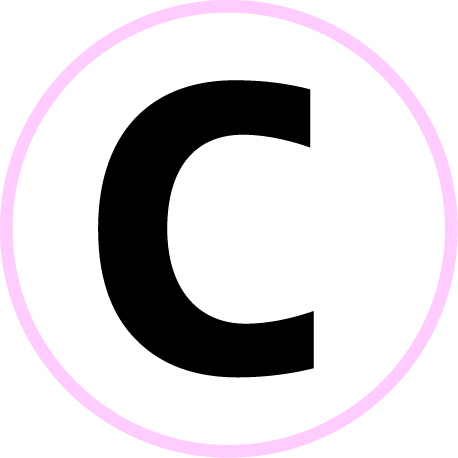 |
|
なるほど。共闘を受ける側も死亡するリスクはあるとはいえ、大体カードが引けるので受ける価値があるというわけですね。 |
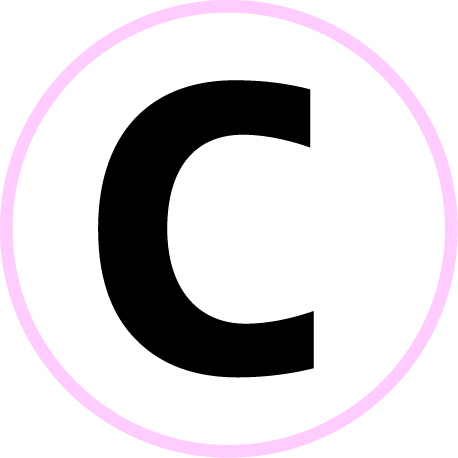 |
|
そういえばそうだった・・・! |

 |
|
しまったドラゴンだ! 勝てない! |
 |
|
なるほど、そういう使い方もできるのか。 |

クリーチャーがターン中に死亡するたびに巨大化していった結果
最終的にエムラクールすら瞬殺するサイズに膨れ上がった《ブレイ/Bulette》
環境最強クリーチャーの1つである《大地教団の精霊/Earth-Cult Elemental》
この2枚が並んで地獄の一丁目になった図。
 |
|
ちなみに直近にホームがあるCさんは初期状態ではまず勝てないので、1/3の確率で即死することになります。 |
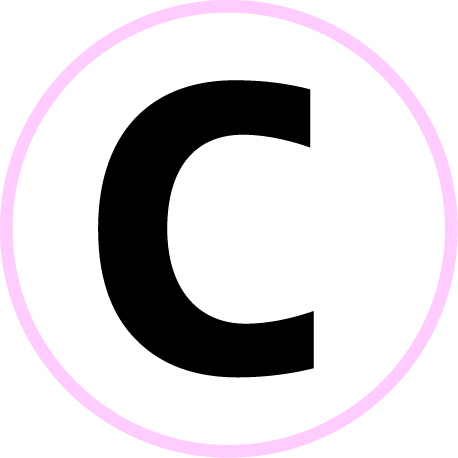 |
|
タスケテ・・・。 |
※こういう状況に陥って除去呪文が無い時は、手札から捨てたカードのマナ・コスト分だけコマを進められる「ダッシュ」を使いましょう。
●みんなもゲームを作ってみよう
今回はフレイバー重視で『フォーゴトン・レルム探訪』のみを使用しましたが、カード選択は自由です。作成者の趣味に合わせて自由にカードを選択しましょう。
デッキ内カードの目安
・2/2の灰色熊で倒せる(相打ち含む)クリーチャー:40%(60枚ルールなら24枚程度)
・2/2の灰色熊で倒せないクリーチャー:40%(60枚ルールなら24枚程度)
・その他の呪文:20%(60枚ルールなら12枚)
・討伐ボーナスを設定しよう
破壊することで宝物を得られる討伐ボーナスクリーチャーを設定します。
ドラゴンの代わりに巨人や《甲鱗のワーム/Scaled Wurm》を選んでもOK。
ゲームバランス的に序盤の灰色熊では倒せない強さを持つクリーチャーを採用すると良いでしょう。
・勝利点を設定しよう
このゲームでは生成カードが多く存在する宝物・トークンを勝利点として採用しましたが、追加の勝利点を設定しても良いでしょう。
例として
・『エルドレインの王権』の食べ物・トークン
・生成したクリーチャー・トークンの数に応じて生成される宝物・トークン
※クリーチャー・トークンは生成した数だけカウントする
・設定したクリーチャーの撃破数に応じて生成される宝物・トークン
等を勝利点として扱ったりするとカードの選択肢が広がって良いかもしれません。
★補足★
・「食べ物と宝物」など、複数のオブジェクトを勝利点として扱う場合
→それぞれを別のパーマネントとしてカウントし、合計の数を勝利点としてカウントする。
・「生成したクリーチャー・トークン」や「撃破数」などゲーム内での行動を勝利点としてカウントする場合
設定したカウント(例:クリーチャーを5体死亡させる)ごとに宝物・トークンを1つ生成する。
・追加ルールを考えてみよう
今回のフォーゴトン・レルム探訪バージョンでは追加ルールとして「ダンジョン」の要素を入れています。
普通にダンジョンを探索する以外に、周回ボーナスとして+1/+1カウンターを置くかダンジョンを探索するかを選べるようにしています。
カードプールによって追加ルールを設定すると面白さが増します。
例えば、灰色熊の冒険なのでプレイヤーキャラクターを《灰色熊/Grizzly Bears》にしていますが
「元祖灰色熊の冒険」のようにクリーチャーを変更できる(ゲーム開始時に選択できる)ようにしても良いかもしれません。
他にも
・イニストラードの昼夜の概念
・ストリクスヘイヴンの履修
・カラデシュのエネルギー
などなど、組み合わせの可能性はサイゼリアのメニューくらい無限大なので作成者の腕の見せどころですよ!
・デッキ枚数を変えてみよう
今回はベーシックルールとしてデッキの枚数を60枚にしていますが、もっと多くのカードを採用したい場合はエキスパートルールとしてデッキ枚数を100枚に増やしましょう。
その場合
-
・墓地は共有ではなくプレイヤーごと
→カードはターンプレイヤーの墓地に落ちます。 -
・灰色熊が死亡した場合、そのプレイヤーの墓地のカードは追放される
→通常の追放と違い墓地に戻りません。 -
・ライブラリーが切れてカードが引けなくなったらゲーム終了
以上のルールを追加すると良いでしょう。
フラッシュバックのような墓地活用や各プレイヤーの墓地を参照するカードが使用できるようになり、カード選択の幅が広がります。
・カード選定等のポイントなど
・当たり前ですが、マジックのカードは灰色熊の冒険と完全互換していません。
このルールに適合しない効果を持ったカードは数多くあるため、そういった混乱を招くカードの採用は控えた方が良いでしょう。
・実際にプレイするとわかりますが、マス上に置くコマをダイスにするとめちゃくちゃ混乱します(2敗)。
ダイストレーを用意したり、コインやちょっとした人形等をコマにすると事故を防げます。
・繰り返し使用できる装備品は非常に強力です。
ゲームバランスに大きく影響するので、弱めの効果を持ったものを採用したり、枚数を抑えると良いでしょう。
・ダンジョンを採用する場合、《ファンデルヴァーの失われた鉱山/Lost Mine of Phandelver》は「占術1」→「宝物・トークン」→「-4/-0修正」→「1ドロー」のルートを通ることになります。
「-4/-0修正」の状態をわかりやすくするために、メモ帳等で簡易的なマーカーを何枚か用意しておくと良いでしょう。
・フォーゴトン・レルム探訪以外の面白いカード
《ハルマゲドン/Armageddon》
マスに置かれている裏向きのカードは土地として扱うので、裏向きに配置したカードを全て無かったことにする豪快なカードです。
墓地を参照する100枚ルールで一気に墓地を増やす手段にもなります。
表向きになっているクリーチャーは破壊できないことには注意。
《ドゥーンドの調査員/Dhund Operative》
最序盤ではただの熊ですが、宝物を獲得したり装備品を手に入れた瞬間接死を持って襲いかかってきます。
ゲームの性質上、接死は非常に強力な能力です。
このようにゲームが進むと強化される能力を持ったクリーチャーを採用するとより面白いゲームになります。
《クローン/Clone》
戦場にいるいずれかのクリーチャーとして出るので、大体0/0のクリーチャーか《灰色熊/Grizzly Bears》になりますが
自分自身が十分に強化されている状態で、倒されずにマスに残っている討伐ボーナスクリーチャーやPIG能力持ちのクリーチャーに変身させて、アドバンテージを得るといったこともできます。
《巨大猿、コグラ/Kogla, the Titan Ape》
めくれた時に他のクリーチャーと格闘してくれる便利なクリーチャー・・・かと思いきや、戦闘時にこちらの宝物や装備品、オーラを破壊してくる非常に厄介なクリーチャーです。
「あなたがコントロールしていないクリーチャーと格闘を行う」と記載されているので、「もしかして自分自身のドラミングで肋骨折って死ぬのでは?」と思うかもしれませんが
灰色熊の冒険においてコントロールするクリーチャーとは自分自身の《灰色熊/Grizzly Bears》とめくれたクリーチャーを指すので、宝物を破壊されたくないのであれば他のめくれている強いクリーチャー等と相打ちしてもらいましょう。
《ヴィトゥ=ガジーの目覚め/Awakening of Vitu-Ghazi》
マスは「あなたがコントロールする土地」として扱うので、裏向きのカードに+1/+1カウンターを置くことでめくれたクリーチャーをめちゃくちゃ強化された状態にすることができます。
このカードをリードしているプレイヤーのホーム前付近に置くことでリスタート時の足止めとして使用することができます。
ちなみにめくれたカードがクリーチャーカードでなかった場合は、既にそのマスがクリーチャー化していようが戦闘は発生しません。
この他にもこいつ・・・「灰色熊の冒険で使うためだけに刷られたのでは???」というカードは探せばたくさんあります!
●おわりに
いかがでしたか!?
大会終わりにこのゲームを持ち込んでみたくなってきませんか!?
まずは60枚ルールのデッキを用意して、ルールブックを4枚印刷するところから始めましょう!
このゲームのスゴいところは、全てマジック:ザ・ギャザリングのカードでできているところです。
つまり! 統率者と同じノリでカードショップで遊べちゃいます!!
カードショップといえば2022年3月22日(火)にドラゴンスター秋葉原駅前店がオープンしました!
もちろんドラゴンスターのデュエルスペースでも遊べちゃうので、今すぐ灰色熊の冒険を組んでドラゴンスター秋葉原駅前店へGO!!!!